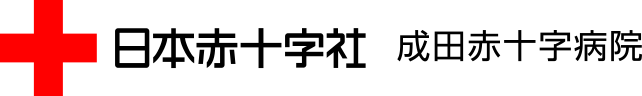
A:急性期医療を行う成田北総地域の基幹病院です。716床の大規模病院で19の診療科を持っています。3次救命救急センターや集中治療室を備えハイリスクの周産期医療や癌治療を行う千葉県がん診療連携協力病院としての役割を果たしています。さらに、赤十字病院として、国内外の災害救護や、いざという時に役立つための知識と技術を普及する目的で救急法や健康生活支援講習等、赤十字講習会も開催しています。
A:日本医療機能評価機構で行っている病院機能評価3rdG:Ver2.0を受審し、平成31年3月1日付で認定されています。
A:急性期病院なので、患者さんの早期回復を願い、心あたたかい看護を目指しています。患者さんから感謝の手紙も多く大変嬉しいことです。また、QC活動、パスの作成や活用、院内研究会等が開かれ看護師のみではなく、職種を超えた院内活動が活発です。
A:こころ温かい看護、安全な看護、専門性の高い看護を目指しています。
A:質が高く心あたたかい看護をめざしています。
A:はかれます。看護師1人1人のキャリアを支えるための「キャリア開発ラダー」を導入しています。ラダーは、主体的にキャリアアップしていけるように新人からエキスパートまでのレベルを5段階にわけて具体的な達成課題を示しています。そして、そのレベルに合わせた研修を受けながらキャリアアップできるようになっています。Iレベル(新人)には、静脈注射研修、フィジカルアセスメント、急変・救急時の看護研修等が組まれています。
A:大学・大学院への進学は、休職や奨学金制度がありますし、専門看護師への支援もしています。認定看護師を目指す方には、出張派遣が認められています。現在、8人の認定看護師がおり、院内はもちろん、院外でも活躍しています。
糖尿病看護、集中ケア、皮膚・排泄ケア、がん化学療法看護、緩和ケア、手術看護、透析看護、感染管理
A:国内で起きた災害に対し、直ちに救護班を派遣し災害医療救護活動を行います。現在救護班12個班を常備しており、円滑な救護活動が出来るよう日々訓練や研修会を行っております。また、国外で起こる様々な災害や紛争等にたいしては、派遣要請に応じて職員を派遣できる体制をとっています。国外派遣については、本社の研修や語学能力が必要となります。
A:就職にあたり、第3希望まで希望をとり、第1希望を優先に勤務場所を決定しています。しかし、希望が集中する場合には、第2、第3希望になることもあります。
A:日勤、準夜勤、深夜勤の3交替制、3人夜勤です。病棟によっては4人夜勤の 病棟もあります。1ヶ月の夜勤回数は、8回です。夜勤の開始は、おおよそ5月中旬から6月頃です。夜勤の見習いをしてから夜勤に入ることになっています。
A:医療安全推進室を設けており、そこには、専従の医療安全推進者・感染管理認定看護師・褥瘡担当認定看護師が配置されています。 更に、各部署には、リスクマネージャーが配置され、委員会を通して組織横断的な活動を行っています。また、労務管理担当者と感染対策委員会が中心となり、職業感染防止としての針刺し事故防止や、予防接種を実施し、労働安全に関する活動をしています。
A:新人教育担当として、プリセプターがいていつも気にかけてくれています。気軽に相談して下さい。また、周囲の先輩たちも温かく見守っています。また、当院には相談の専門家として、臨床心理士が3名配置され、メンタル面のサポートをしています。
A:日本赤十字社の全社的な福利厚生制度があります。全国の宿泊施設・学習・健康関連サービス等が会員割引で受けられます。また、院内にはコンビニエンスストアがあります。子育て支援として育児休業は3年まで可能です。併設の託児所にて夜間託児もしています。
看護部の福利厚生については「福利厚生・処遇」ページをご確認ください。
保養・宿泊・あらゆる生活支援サービス事業
大手福利厚生事業会社と提携して、ありとあらゆるサービス(宿泊、アウトドア、ビューティー、グルメ、カルチャー、フィットネス、エンターテイメントなど)を総合的に行っております。
職員及びご家族の方も利用できます。
慶弔見舞金制度は、職員及びご家族の方に支給する制度です。
永年勤続記念品制度は、10年以上の節目の年に、規定の旅行券を支給する制度です。
東京海上日動、三井住友海上火災、損保ジャパン、あいおい損保の4社と提携して、一般価格よりも割安な保険料(20%割引)で自動車保険に加入することが出来ます。職員本人だけでなく、ご家族の方も契約できます。
ガソリン割引制度は、大手ガソリン販売会社と提携して、一般価格よりも安く購入することができます。
当院とスターツ(ピタットハウス)株式会社との契約により、入社時に賃貸借の契約手数料を10%割引する制度です。
職員が私傷病等のため勤務することができず、給与の支給を受けることができない場合に、給与を保障する制度です。
育児休業に関しても、復帰6ヶ月後に10万円が支給されます。
職員が自己啓発のための講習、講座を受講したときに費用の一部を補助する制度です。要件は職員1人あたり年1回1講座で、受講費用の3分の1の額(補助上限額は10,000 円)となります。
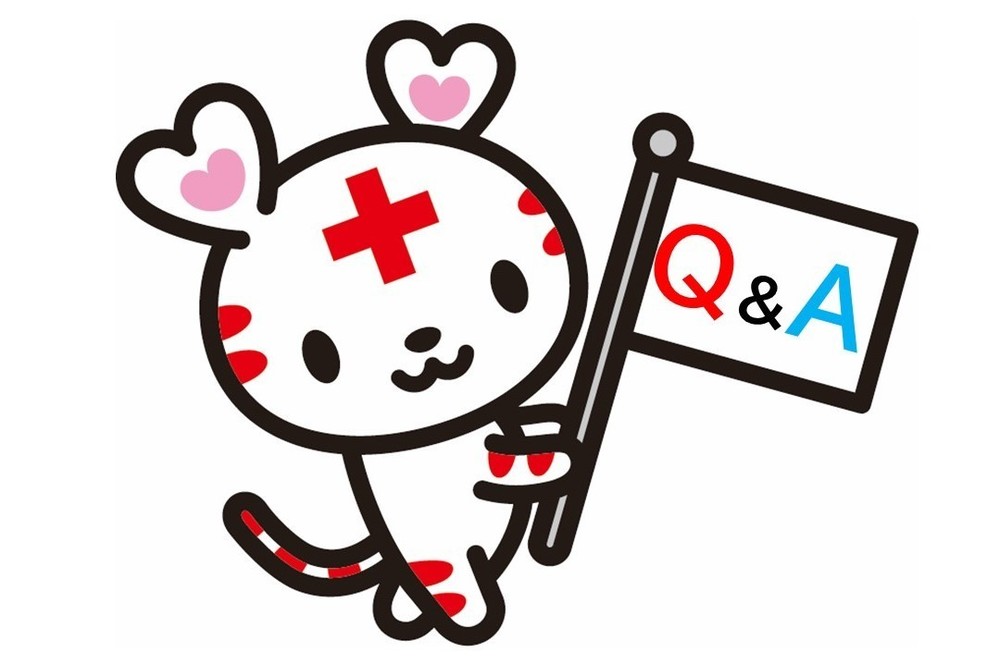
第2階層のインデックページに表示させる画像のため削除しないでください。(横幅680px以上の横型の画像を1枚のみ設定してください)
【この画像とテキストは、ページの公開時には表示されません】
 JMIP認証病院
JMIP認証病院 日本医療機能評価機構
日本医療機能評価機構